福岡市でウェブ制作、システム開発をしておりますYAMAMOTO CREATE代表の山本です。独立してからというもの、本当にありがたいことに、日々新しい出会いや学びの連続です。
先日も、あるWebデザイナーさんと打ち合わせをさせていただきました。 高坂さん(https://nn-design27.com)という、非常にパワフルで、何より「人の課題」に真摯に向き合う、本当に素敵な女性のデザイナーさんです。(高坂さんのInstagramはこちら:https://www.instagram.com/nn.design07)

その高坂さんが、本当にワクワクするようなプロジェクトを持ってきてくれたのです。
「山本さん、今、軽運送業者さんたち、すごく困ってるみたいなんです」
彼女が持ち寄ってくれたのは、単なる「アプリ開発案件」ではありませんでした。それは、僕らの便利な生活を最前線で支えてくれている「軽運送業者さん」たちが抱える、生々しいニーズや課題の数々でした。
こんな話聞いてたらそりゃテンション上がるしめっちゃワクワクしちゃうじゃないですか。それと同時に、僕らのようなWebデザイナーやエンジニア、いわゆる「何かを創る人」の存在意義について、改めて深く、深く考えさせられたんです。
最終的に僕の中で着地したのは、「困っている人を助ける」という、とてもシンプルで、けどめちゃくちゃ大切な「ビジネスの原点」でした。
WantsとNeeds

僕はこれまで、「こんな機能が欲しい」「こんなサイトを作りたい」といった、お客様の「ご要望(Wants)」にお応えする形での開発を手がけてきました。それはもちろん、お客様から報酬をいただいてクリエイティブを創る以上、当然だと思ってます。
しかし、高坂さんが持ってきてくれたのは、なんと言ったら良いんでしょうかね。 「こういうアプリを作ってほしい」というオーダーではあるんですけど、「こういう人たちが、こんなことで困っている。これを、山本さんの技術で何とか助けられませんか?」という、純粋な「課題(Needs)」だったのです。
その熱量と、課題の裏側にある現場の切実な声に引き込まれました。
知られざる「現場の悲鳴」
僕らの便利な社会は、彼ら軽運送ドライバーさんたちの奮闘によって支えられています。しかし、僕らが想像する以上に、彼らは「荷物を運ぶ」というメイン業務以外に、多くの「見えない業務」に追われていました。
高坂さんがヒアリングしてくれた、現場の「困った」は、実に切実なものでした。
毎日の記録という「見えない重圧」
まず、法律で定められた毎日の「アルコールチェック」とその「記録」。 安全運転のため、法律で義務付けられている毎日のアルコールチェック。もちろん、誰もが必要なことだと理解しています。しかし、問題はその「記録と報告」の手間です。
業務の開始前と終了後の1日2回。指定されたチェッカーで測定し、その数値をスマホで撮影し、報告する…。朝の忙しい時間にも、一日の業務を終えてクタクタに疲れた体にも、この「報告義務」が重くのしかかります。
これは単に「時間がかかる」という話ではありません。朝起きた瞬間から「あ、今日もあれをやらなきゃ」と思い出し、一日の終わりにも「あ、まだ報告が残ってた」と気づく。この心理的なプレッシャーが、日々の業務に重くのしかかっているのです。
疲れた体で向き合う「記憶との戦い」
次に待っているのが、一日の業務を記録する「日報」です。 その日に運んだ荷物の数、走行距離、休憩時間…。運転に全神経を集中させた後、これらの細かい数字を記憶から呼び起こし、紙やExcelにまとめる作業。
「本当は、軽トラの運転席で、スマホで全部終わらせたい」
高坂さんから聞いたこの現場の声は、彼らの置かれた状況のすべてを物語っていました。彼らはプロとして、日報の必要性を理解しているからこそ、それを正確に記録しようとします。しかし、一日の終わりに疲れた頭で記憶を辿るのは、まさに「戦い」です。これはもう「面倒くさい」を通り越して、本来ならば休むべき時間を削って行う「時間外労働」に近いものがあります。
月末に訪れる「専門外業務」という名の壁
そしてフリーランスなら誰もが頷くであろう、月末の請求書発行業務。 インボイス制度が始まり、ただでさえ慣れない事務作業がさらに複雑化しています。「ちゃんとしたフォーマットがわからない」「作成がとにかく面倒」…。
「荷物を運ぶプロ」である彼らが、専門外である経理作業に頭を悩ませ、貴重な時間を奪われている。これもまた、解決すべき大きな「困りごと」でした。
これは単に「面倒」なだけではありません。「もし間違っていたらどうしよう」「税金の計算が合っているだろうか」という「不安」が常につきまといます。この精神的な負担こそが、最も解決すべき課題だと感じました。
僕らは、何のために「創る」のか?
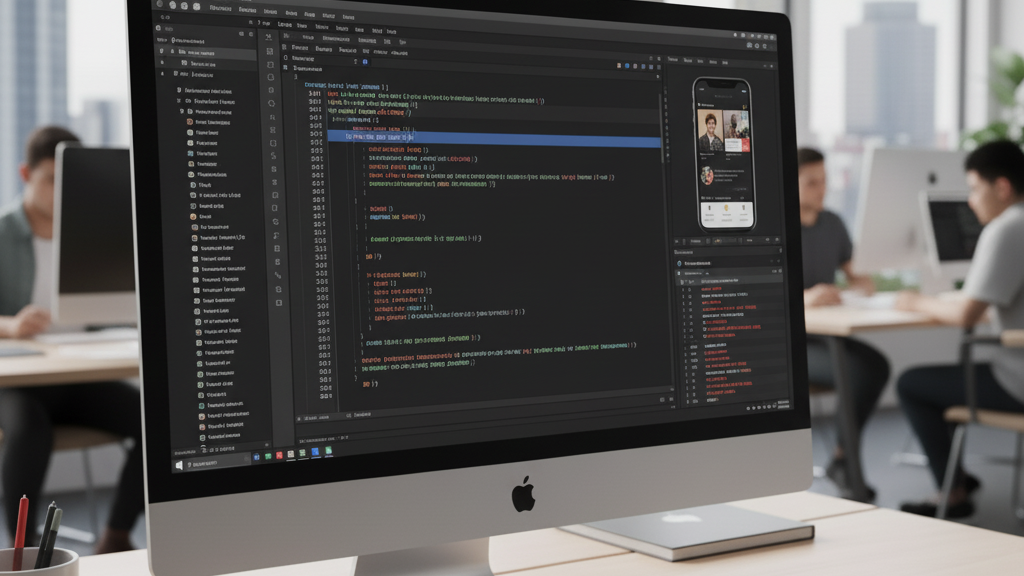
高坂さんとこれらの課題について深く話しているうちに、僕はハッとさせられました。 僕ら「創る人(クリエイター)」は、一体何のためにいるんだろう?と。
日常の業務に追われていると、つい「いかに効率よくコードを書くか」「いかに美しいデザインを作るか」ということばかりに目が行きがちです。
もちろん、人の心を動かすような美しいデザインを創ることも、最新の技術を駆使して革新的なシステムを構築することも、非常に価値のある仕事です。
でも、それらはすべて「手段」であって、「目的」ではないはずです。
目の前に、これだけ具体的に「困っている」人たちがいる。 「毎朝の報告が大変なんです」 「日報を書く時間が辛くて…」 「請求書の作り方がわからなくて、月末が憂鬱なんです」
この一つひとつの切実な「困った」に対して、 「あ、それ、僕らの技術を使えば、こうやって解決できますよ」 と、そっと手を差し伸べること。
例えば、アルコールチェックの写真をスマホで撮るだけで、AIが数値を読み取り、日時や位置情報と合わせて自動で報告が完了する。 例えば、スマホで数回タップするだけで、日報がフォーマット化されて自動で送信される。 例えば、アプリに必要な情報を一度登録するだけで、ボタン一つでインボイス対応の請求書がPDFで発行される。
僕らが必死で学んできたデザインの知識や、プログラミングのスキルは、まさにこの瞬間のためにあるのではないでしょうか。
スキルとは「誰かを助けるため」の道具である
誰かに技術力をひけらかすためじゃない。ましてや、自己満足のために複雑なものを創るためでもない。ただ純粋に、目の前にいる誰かの「不便」や「苦痛」を取り除き、その人の毎日をほんの少しでも楽にするため。その人の時間を取り戻し、笑顔にするためにあるんだと。
これこそが、商売の、いや、ビジネスというものの「原点」だと思うんです。 誰かの「困った」を見つけ、それを自分たちのスキルで解決する。その対価として、お客様から「ありがとう」という言葉と、報酬をいただく。
僕がなぜ会社員を辞め、個人事業主として独立したのか。それは、自由になりたかったという以上に、「この人のために作りたい」と心から思える仕事を選びたかったからです。
高坂さんが持ってきてくれたこのプロジェクトは、僕が独立時に誓った、この一番シンプルで、一番大切なことを、改めて思い出させてくれました。
「ありがとう」を創る、これからのコラボレーション
今回の打ち合わせは、僕にとって単なる「名刺交換」の時間を遥かに超える、自分の仕事に対する姿勢や「存在意義」を改めて正してくれる、本当に貴重な時間となりました。
こんなにも本質的な気づきを与えてくれた高坂さんには、本当に感謝しかありません。
これはもう、YAMAMOTO CREATEだけのプロジェクトではありません。 現場の「痛み」に心から共感し、それをすくい上げるデザイナー(高坂さん)と、その「痛み」を取り除く「道具」を形にできるエンジニア(僕)。この二者がタッグを組むからこそ、本当に価値のあるものが創れるのだと確信しています。
これから高坂さんという素晴らしいデザイナーさんと一緒に、このプロジェクトをどう形にしていくか。ドライバーさんたちの「困った」を、僕らの「創る力」で、どうやって「感動」や「笑顔」に変えていけるか。
そう考えただけで、楽しみで仕方がありません。
YAMAMOTO CREATEは、これからも「誰かの困った」に真摯に寄り添い、ITという名の「優しさ」で、それを解決するサポートを全力で続けていきます。